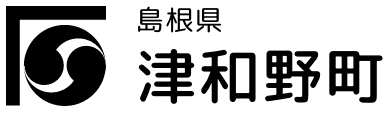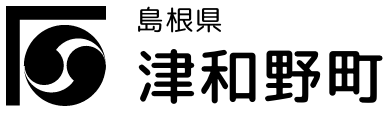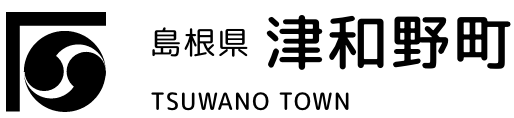概要
限度額適用認定証を医療機関に提示することにより自己負担額(一部負担金)が自己負担限度額(注1)までとなり、窓口負担が軽減されます。
申請した月の1日からの適用となりますので、適用を受けようとする月の末日までに申請により認定証の交付を受け、同じく月の末日までに医療機関へ提示 してください。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
(注1)自己負担限度額については、関連情報「医療費が高くなったとき(高額療養費)」をご確認ください。
対象者
国民健康保険に加入している方で、かつ保険税の滞納がない方。(ただし、滞納税の納税相談の上、発行可)
必要なもの
- 国民健康保険資格確認書
- 同居のご家族以外の方が申請するときは代理人選任届
手続方法
必要なものをそろえ、役場本庁舎・税務住民課 総合窓口、津和野庁舎・健康福祉課までお越し下さい。
受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。
交付される認定証
|
区分(注2) |
交付される認定証 |
| 70歳未満の方 | 限度額適用認定証(ア・イ・ウ・エのいずれか) |
| 70歳未満の住民税非課税世帯 |
限度額適用認定証(オ) 標準負担額減額認定証 |
| 70歳以上の低所得【1】、【2】 |
限度額適用・標準負担額減額認定証(注3) |
| 70歳以上の一般 | 必要ありません(資格確認書を提示することにより限度額の適用を受けられます) |
| 70再以上の現役並み所得者【1】、【2】、【3】 |
限度額適用認定証(【1】、【2】の方) |
(注2)区分については、関連情報「医療費が高くなったとき(高額療養費)」をご確認ください。
(注3)入院時の食事代の減額にかかる認定証も兼ねています。
入院時の食事代については、関連情報「入院時食事療養費」をご確認ください。
※ 国保税を滞納している方には認定証を発行できない場合があります。
※ 当該入院費用以外にも高額療養費の合算対象となる医療費を負担をしたときは、追加支給を受けられる場合がありますので、高額療養費の申請をしてください。
サイト内の関連リンク情報
このページを見た方はこんなページも見ています
このページに関する
お問い合わせ先
- 津和野庁舎 健康福祉課
-
- 電話番号: 0856-72-0651
- FAX番号: 0856-72-1650