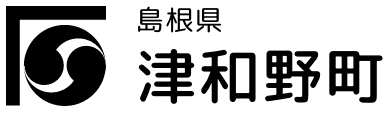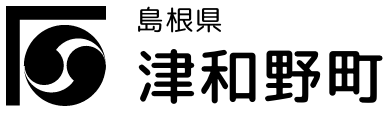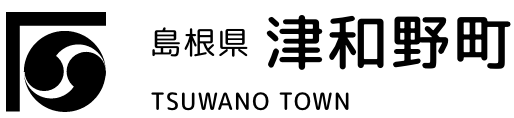地域活性学会の研究大会が浜田市の島根県立大学で開催され、シンポジウムのパネラーとして参加してまいりました。
当学会は、「わが国の重要な社会課題、政策課題である地域活性化をアカデミズムの立場から支援する」ことを趣旨として平成20年に設立されており、「学術研究者の分析とともに地域で実際活動をおこなっている種々民間団体、さらに制度・予算の面で支援する行政主体の参加も募り、より実践的な政策提言・地域活性化の取組支援につながる学術研究活動」を行っておられます。
研究大会は年1回全国各地を持ち回りで開催されており、この度は島根県立大学での開催となりました。
テーマを「過疎地における地域活性化~地域と自治体の共創~」とし、「過疎法の制定に大きな役割を果たし、『過疎発祥の地』ともいわれた美濃郡匹見町を含む島根県において、現代の過疎地の実態とそれに対する地域と自治体、そして、両者が共同した取組、担い手の育成について探求し、共有」することを開催趣旨とされております。
大会は6日から9日までの3日間に渡って行われ、初日の首長シンポジウム「わがまち一押しの施策」の中で、川本町長、美郷町長、海士町長、江津市長、出雲市長とともに、私もパネラーの一人として声をかけて頂いたしだいです。
「わがまち一押しの施策」というタイトルでありますが、私からは「県外からの高校留学生による地域活性化研究」と題して、これまでの津和野高校の魅力化と生徒数増の取り組みや今後の方向性などについて発表いたしました。
津和野高校と連携を図り、魅力化コーディネーターの配置や町営英語塾HAN―KOHの設置、(一財)つわの学びみらいの組織化、そして「まち全体が学びの場」として位置づけての様々な実践活動の取り組みを、全国からお越しになられた会員の皆さまにお話をさせて頂きました。
短い時間の中でありましたので、十分に理解して頂ける説明には至らなかったと思いますが、それでもこの度の発表を通して、発表資料の作成の準備段階も含め私自身が、これまで紆余曲折はありながらも、高校魅力化の取り組みがしっかりと実を結んでいることを改めて実感する機会となりました。
歴史上において、そして現代に至るまで自らの道を切り開き社会で活躍する人材を数多く輩出してきた「教育のまち・津和野町」が、未来へ向けても進んで行くまちづくりの柱となることの思いを強くしたところでもあります。
現在は、津和野高校の成果を更に発展させるべく、幼児期から小中高校までにつながる一貫したキャリア教育とふるさと教育を保育園や学校と地域、家庭、行政が連携し推進する0歳児からのひとづくりを進めております。
教育の魅力化を人口減少対策につなげて行く取り組みはもちろん大事ですが、「教育のまち・津和野町」としての伝統を重んじ、生きる力をもった津和野人をつくるという使命を忘れることなく、信念をもって進んで行きたいとも思っております。