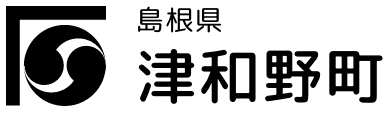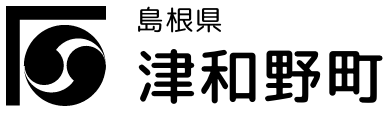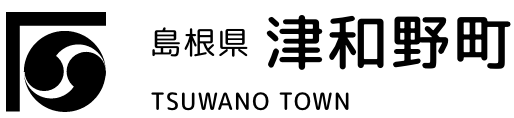概要
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、自己負担額が高額になったときは、国保・介護を合わせた自己負担限度額(毎年8月~翌年7月までの年額)が適用されます。
対象者
同じ世帯で医療と介護の両方を受けている人が対象となります。
自己負担限度額について
自己負担限度額は、世帯員の年齢や所得によって、下の表のように、細かく設定されています。年額を計算する1年間の期間は、毎年8月1日~翌年7月31日までで、支給の申請は翌年8月1日から行うことができます。
高額医療・高額介護合算療養費制度の自己限度額表
70歳未満の人
|
所得区分 |
限度額 |
||
| ア |
年間所得901万円超 |
212万円 |
|
|
イ |
年間所得600万円超901万円以下 |
141万円 |
|
| ウ |
年間所得210万円超600万円以下 |
67万円 | |
| エ |
年間所得210万円以下 |
60万円 | |
| オ |
住民税非課税世帯 |
34万円 | |
※年間所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
70歳以上75歳未満の人
| 課税区分 | 限度額 | ||
| 現役並み所得者 | 【3】 |
課税所得690万円以上 |
212万円 |
| 【2】 | 課税所得380万円以上690万円未満 | 141万円 | |
| 【1】 | 課税所得145万円以上380万円未満 | 67万円 | |
| 一般 | 56万円 | ||
| 低所得者【2】 | 31万円 | ||
| 低所得者【1】 | 19万円 | ||
対象となる世帯に、70歳~74歳の方と70歳未満の方が混在する場合には、
- まずは70歳~74歳の方に係る自己負担の合算額に、70歳~74歳の区分の自己負担限度額が適用され(70歳~74歳の方について、医療と介護の両方の負担が生じている場合に限ります。
- (1)のなお残る負担額と、70歳未満の者に係る自己負担の合算額とを合算した額に、70歳未満の区分の自己負担限度額が適用され、(1)と(2)で算出した額の合計額がその世帯の支給額となります。
高額医療・高額介護合算療養費制度では、医療保険と介護保険の双方から、自己負担額の比率に応じて支給される仕組みになっています。そのため、支給を受けるためには、加入している医療保険と介護保険の両方の窓口に申請することが必要です。時期によっては、申請を行ってから支給を受けるまでには、一定の時間がかかります。
- 介護保険に申請する
- 医療保険に申請する
- 支給額が決定される
- 医療保険・介護保険それぞれから支給される
必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 振込先金融機関の口座番号のわかるもの(預金通帳など)
手続方法
対象となると思われる方には、役場よりお知らせが届きます。詳しい手続等はお知らせをご覧ください。手続場所は役場本庁舎・税務住民課 総合窓口、津和野庁舎・健康福祉課で、受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。
このページを見た方はこんなページも見ています
Contact
このページに関する
お問い合わせ先
- 津和野庁舎 健康福祉課
-
- 電話番号: 0856-72-0651
- FAX番号: 0856-72-1650