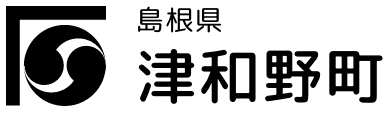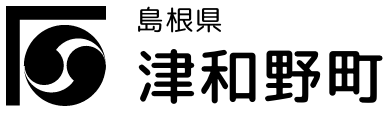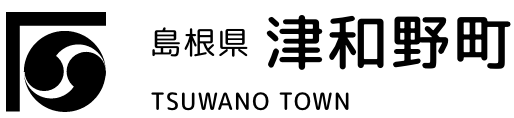農地貸借制度の改正について
農業経営基盤強化促進法等の一部改正に伴い、令和7年度より利用権設定(相対での農地貸借制度)が廃止され、農地中間管理機構を介した農地中間管理事業による貸借(農用地利用集積等促進計画)が行われています。
農地の貸し借りについて
農地の貸借契約は
(1)農地法第3条に基づく貸借
(2)農地中間管理機構を介した貸借(農用地利用集積等促進計画)
のどちらかになります。上記の2種類の貸借の違いについては次の表を参考にしてください。
|
|
農地法第3条に基づく貸借 |
農地中間管理機構を介した貸借 (農用地利用集積等促進計画) |
|
貸借形態 |
貸主と借主との直接の貸借 |
農地中間管理機構を通した貸借(貸主⇒機構⇒耕作者) ※貸主は機構に農地を貸しますが、耕作者がいる場合でないと機構への貸借は基本的にはできません。 |
|
契約年数 |
任意(50年以内) |
3年以上(耕作者の安定経営のために10年以上が推奨されています。) |
|
要件等 |
農地法第3条の許可要件を満たす必要があります。 |
基本的には地域計画内の農地が対象となります。また、耕作者は地域計画に位置付けられた農業を担う者である必要があります。 貸主が相続登記を完了していない場合は、法定相続人の1/2以上の同意が必要となります。 |
手続きの方法について
これまでの農地貸借が終了する際には、事前に連絡文書を送付しますのでそちらの内容を確認し、継続される場合は同封している「農地貸借申出書」を提出してください。新規に農地の貸借をお考えの方は、貸借方法を確認する必要がありますので、役場農林課までお問い合わせください。
※これまでの利用権設定では農地の貸借開始時期の2ヵ月前までに申請書を提出していただいていましたが、農用地利用促進等促進計画では事務処理に3ヵ月位必要であることが想定されていますので、農地の貸借をお考えの場合はお早めにご相談ください。
ダウンロード
このページを見た方はこんなページも見ています
このページに関する
お問い合わせ先
- 津和野庁舎 農林課
-
- 電話番号: 0856-72-0653
- FAX番号: 0856-72-1650