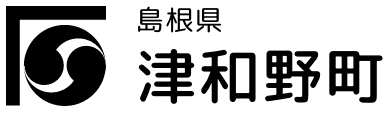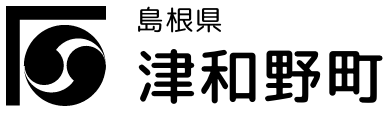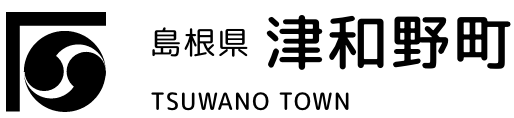津和野町の住まい
生活を支える、なくてはならない「住まい」
一軒家でも集合住宅でも、たったひとつの自分の「城」を探しましょう。
津和野町には次の種類の住宅があります。
それぞれに特徴がありますので、希望するライフスタイルに合った住宅を選ぶことが大切です。詳細についてはお問い合わせください。
空き家情報バンク
「空き家情報バンク制度」は、町内で空き家となった物件情報を登録し、津和野町への定住を希望される方へその情報を紹介する制度です。
詳細はこちら:津和野町空き家情報バンク
公営住宅等
津和野町や島根県など地方自治体等が運営している賃貸住宅です。
詳細はこちら:その他住宅情報
民間住宅
津和野町内の民間賃貸集合住宅で、管理者の承諾が取れたものを紹介しています。
詳細はこちら:民間賃貸集合住宅一覧
津和野町への移住の流れ(一例です)
STEP1:調べる・相談
HP等で津和野町の事を調べてみましょう。
さらに詳しく知りたい方はお気軽に役場にお問合せ下さい。
STEP2:移住体験
津和野町の雰囲気を直に体験して下さい。
空き家見学、農業体験、教育関連施設見学など可能です。
STEP3:住まい・仕事を決める
自分の条件にあった住まいや、希望する仕事を探しましょう。
お困りの際はご相談下さい。
STEP4:移住
つわの暮らしスタート!
UIターン者の声

鈴木英雄、桂子さん
鹿児島県奄美群島よりIターン・家族(夫婦)
津和野町に移住後、英雄さんは美術創作とYoutubeで「津和野点描」(英すけっぷ)などをアップしている。妻の桂子さんは津和野をイメージした布人形制作の合間に「鷗外の輪読会」「歩こう会」などに参加している。
移住のきっかけ
20年間住んでいた奄美加計呂麻島の「離島暮らし」から、老後を「豊かな文化と里山の暮らし」にチェンジしたかったからです。森鷗外や安野光雅さんを生んだ風土と情緒ある風景に惹かれました。
津和野の気に入っているところ
津和野川沿いの散歩、誠実な人々、程よく身近で生活が成り立つところ。
今後の展望・気持ち
感謝を忘れずに、気持ちをフレッシュに保ち、穏やかに老後を送りたい。また、地域の子ども達と創造的なふれ合いができたらと思います。

岡崎隼大さん
福岡県よりUターン・家族(妻、子1人)
祖母の実家のある津和野町に移住。移住後、働いていた職場の先輩から「一緒に栗をやらないか?」と誘われたのがきっかけで、本格的に農業を始める事となった。農業の研修期間中に、町内の先輩農家と栗の新植を行ったが、成木化し収穫量が安定するのは5年以上期間を要する。収益が得られるまでの期間、栗園の管理を行いながら、津和野町特定地域づくり事業協同組合の職員として働いている。
津和野の気に入っているところ
近所の方など人との繋がりがあるところです。栗園の管理の手伝いや、新しく栗を植える場所を教えてくれたりします。仕事でも生活でも色々教えてくれる親切な師匠が沢山いるところですね。妻は都会からのIターンで、移住する前は戸惑っていましたが、買い物も不便はなく、病院も近くにあるし、仕事も安定しているようなので今の所大きな不満はなさそうです。
今後の展望
最終的な夢は津和野町の土地(農地)を荒らさないように守っていきたいです。その為に栗を植えていきたいですね。そして、これから新しい人が移住してきた時に栗園を譲っていきたいと思っています。またこっちに来てから地域の人達が困っている事を一緒に解決していきたいと考えるようになりました。地域の皆様は盛り上げる為のアイデアを沢山持っています。でもそれを実行するための若い力が不足していると思うので、自分の力が少しでも役に立てば嬉しいですね。
このページを見た方はこんなページも見ています
このページに関する
お問い合わせ先
- 本庁舎 つわの暮らし推進課
-
- 電話番号: 0856-74-0092
- FAX番号: 0856-74-0002