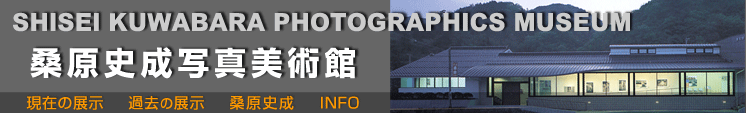 |
||
|
||
| 桑原史成写真展 第4期 『東日本大震災』 -東日本大震災から15年- 2026.1.16~2026.4.15 ※休館日:木曜 |
 ©桑原史成 2011 |
| 今回の展示は、『東日本大震災』を展示します。 2011年3月11日に宮城県沖130kmの太平洋を震源地として、マグニチュード9.0とされる「東日本大震災」が発生したのです。それから今年は15年の節目を迎えました。 僕が被災地の取材、撮影に東北の現地を訪れたのは約3週間後の3月下旬でした。後輩の写真家が同行してくれ、10日間ほど被災地の各地を周りました。ワンボックスの車に燃料をはじめ食料、水、暖房の毛布などを用意しての出発です。大まかな取材の道程を記述すると、首都圏から東北自動車道で岩手県の盛岡に行き、そこから太平洋側陸地の被災地・宮古市に入りました。撮影を開始したのはここからです。次に行程の被災地を順次、記載してみます。 宮古市→重茂→山田町→釜石市→大船渡市(ここから宮城県)→陸前高田市→気仙沼市→南三陸町→石巻市→女川町→東松島市→松島町→七ケ浜町→多賀市→仙台市(宮城野区、若林区)→名取市→岩沼市→亘理町→山元町(ここから福島県)→新地町→相馬市→南相馬市→浪江町→双葉町→大熊町→楢葉町→広野町→いわき市→茨城県→千葉県で撮影を終了しました。 東北大震災で津波による死者は、22,332人とされている。津波の高さは10数メートルとされ、河川を遡った距離は最長で40kmと報告されています。 そして被災が近未来に続く大事故は、福島原発1号の廃炉の問題ですね。原子核が溶解して、未だ効果的な廃炉の作業が鈍座したままです。僕は2011年からコロナ禍の起きる前まで福島原発の周辺を年に一度の企画で撮影を継続してきました。展示の写真にはそれらの写真も合わせて展示しています。 報道写真家 桑原 史成 |
|
SHISEI KUWABARA MUSEUM OF PHOTOGRAPHY
|
